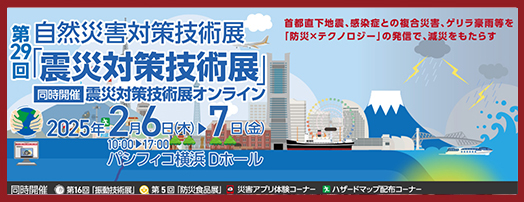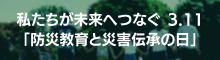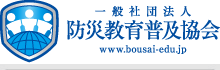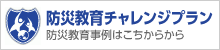このセミナーは終了しました。
2017年9月13日(水)をもって定員となりました。
既にお申込みをされた方でやむを得ずキャンセルされる方は、お手数ですが事前に事務局(03-6822-9903)までお知らせください。
はじめに
相次ぐ自然災害を受け、防災教育への期待と関心はますます高まっています。一方で具体的なノウハウの普及や効果の検証など課題も残されています。弊会では、こうした課題の解決に向けて様々な分野の専門家、有識者の知見を結集し、効果的な防災教育の普及啓発に取り組んでおります。
『防災教育指導者育成セミナー』は、防災教育の指導者として活動を希望する方、防災教育に幅広く関心のある方を対象に「防災教育の指導において重要な知識や事例、体験」を提供するセミナーとして開講されています。
平成28年に第1期地震編を開講し、多くの皆さまにご参加いただきました。平成29年度第2期はテーマを気象とし、東京大学地震研究所共催で開催いたします。防災教育指導に関心のある皆さまのご参加をお待ちしております。
一般社団法人防災教育普及協会
===【実施概要】===
1.名称 「第2期防災教育指導者育成セミナー気象編」
2.日時 2017年10月13日(金) 13:00-17:30
3.場所 東京大学地震研究所 1号館2階セミナー室
4.主催等 主催:一般社団法人防災教育普及協会 共催:東京大学地震研究所
5.資料代 3,000円(2017年度年会費納入済みの弊会会員の方は無料です)
【 非会員の方 】
期日までに入会をご希望のうえ、お申し込みされた方には本セミナー及び今年度実施のセミナーの資料代・参加費等を無料とさせていただきます。
6.参加申し込み方法(9月27日(金)まで)
2017年9月13日(水)をもちまして定員となりました。
参加申込フォーム をクリックして必要事項をご入力ください。募集要項 、受講申込書 によりお申込みいただくこともできます。受講申込書は郵送またはFAX(03-3556-8217)にてお送りください。
7.第2期防災教育指導者セミナー気象編「修了証」の発行
セミナーを修了された方には「修了証」を発行します。
8.内容
13:00-13:10 開会挨拶、事務連絡
13:10-14:10 『気象庁による防災教育支援の取り組み事例』
気象庁総務部 情報利用推進課 安全教育支援係長 中代 誠
14:20-15:20 『防災科学技術研究所による防災教育の実践事例』
国立研究開発法人 防災科学技術研究所
気象災害軽減イノベーションセンター センター長補佐 中村 一樹
15:30-16:30 『防災教育に活用できる教材紹介』
一般社団法人防災教育普及協会 事務局長 宮﨑 賢哉
16:40-17:10 『生徒の主体的活動を生かした気象教育』
田園調布学園中等部高等部 荒川 知子
17:10-17:20 閉会挨拶
東京大学地震研究所 教授
一般社団法人防災教育普及協会 会長 平田 直
17:20-17:30 修了証授与、事務連絡
※講師・プログラム・時程は都合により変更となる場合があります。
9.問い合わせ
一般社団法人防災教育普及協会(担当:宮崎・小野・橋本)
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-15-2 九段坂パークビル3F
TEL.03-6822-9903 FAX.03-3556-8217 http://www.bousai-edu.jp
10.お知らせ
10月14日(土) 13:00-16:00『防災教育交流フォーラム2017』
10月15日(日) 10:00-16:00『防災教育チャレンジプラン中間報告会』
東京大学地震研究所を会場に、防災教育に関する有識者や実践者が集まるフォーラムや実践報告会が開催されます。参加をご希望の方は、HP(http://www.bosai-study.net/top.html )にてお申込みください(14日、15日はいずれも無料です)。
===【広報資料】===
ご関係の皆さまへのお知らせ等でご活用ください。
▶ 第2期防災教育指導者育成セミナー気象編チラシ



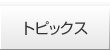
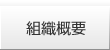
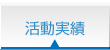
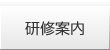
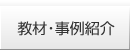
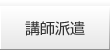

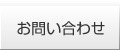

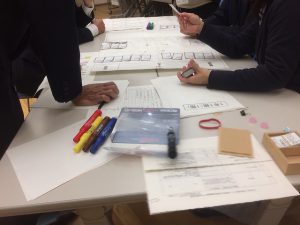


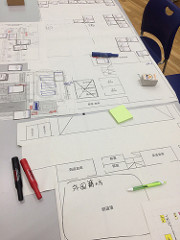


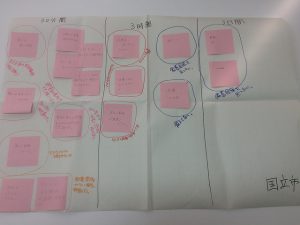 都内の社会福祉法人が運営する保育園の新入職員研修を担当しました。
都内の社会福祉法人が運営する保育園の新入職員研修を担当しました。