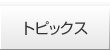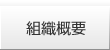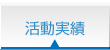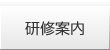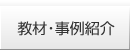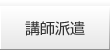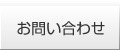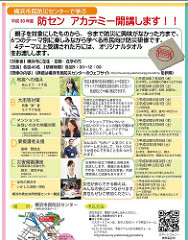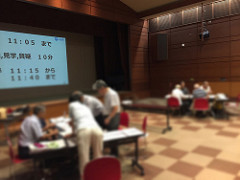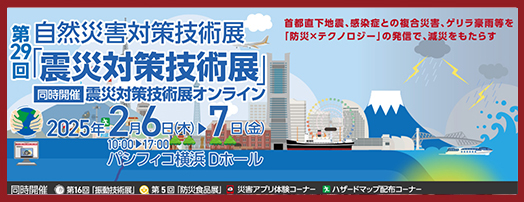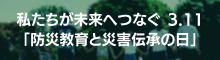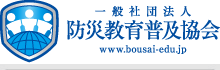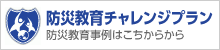明治大学第21回ホームカミングデーで、同大学震災等復興活動支援センターが行う「防災キッズワークショップ」を宮﨑事務局長が担当し、2時間という限られた時間でしたが100名以上の親子連れが参加しました。
「防災キッズワークショップ」では、宮﨑事務局長が作成した防災教材『うさぎ一家のぼうさいグッズえらび』や『防災ビンゴ』を用いて、15分程度で小さな子どもから保護者まで、誰もが楽しく防災・減災を学べるプログラムを実施しました。
参加者からは「とても役に立つワークショップだった」「家族によって必要な防災グッズが異なることがわかった」という声をいただきました。
※『うさぎ一家のぼうさいグッズえらび』、『防災ビンゴ』の資料提供をご希望の方はお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。